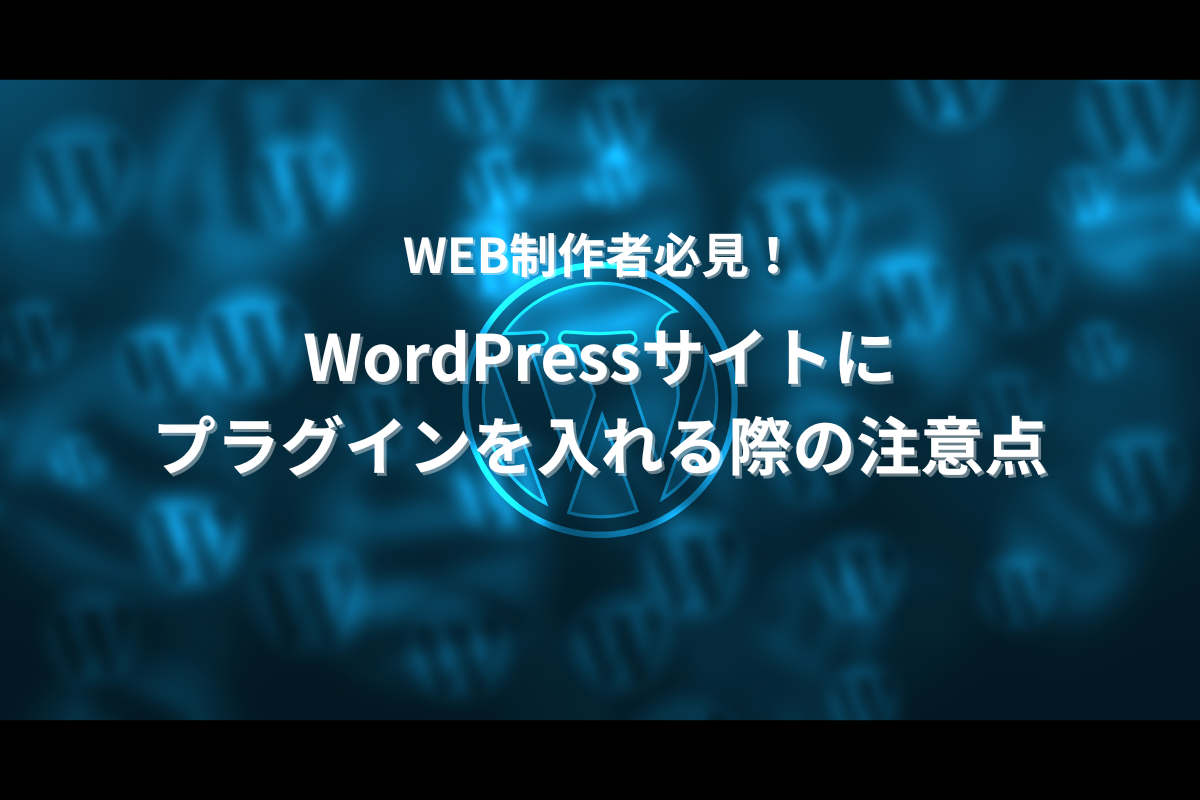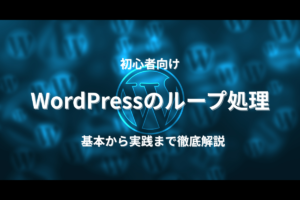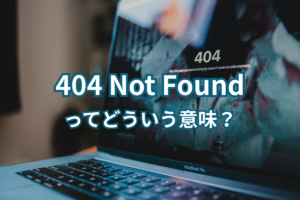WordPressでWeb制作を行う上で欠かせないのが「プラグイン」の存在です。
しかし、プラグインは便利な反面、セキュリティや保守性のリスクを伴うものでもあります。
この記事では、Web制作に携わるすべての人が知っておくべき、
WordPressプラグイン導入時の注意点を、実例とともにわかりやすく解説します。
プラグインは便利だけど、リスクとなる面もあるよ。
なぜプラグインがリスクになりうるのか?
プラグインは、WordPressの機能を簡単に拡張できる便利なツールです。
しかし、以下のような理由でサイトの安全性を脅かす要因にもなり得ます。
- プラグインの脆弱性が悪意ある攻撃者に悪用されることがある
- メンテナンスされていないプラグインが放置されている
- 互換性のないプラグイン同士が競合し、不具合を起こす
プラグインは入れれば入れるほど便利になる一方、
同時にセキュリティホールの数も増えていくと考えるべきです。
導入前に必ず確認すべき「プラグインの最終更新日」
WordPress公式リポジトリには、各プラグインに「最終更新日」が記載されています。
これはそのプラグインが現在も開発・保守されているかを見極める重要な指標です。
✅ チェックポイント
- 半年以上更新されていないプラグインは基本的に避ける
- PHPやWordPress本体のバージョンと互換性があるか確認する
- 開発者情報や、他のユーザーのレビューも参考にする
[ポイント]
プラグイン開発者が長期間更新していないプラグインは、
脆弱性が修正されないまま放置されている可能性があります。
プラグイン導入時のセキュリティ対策
🔐 脆弱性情報を定期的にチェック
Web制作者として、脆弱性情報の確認は必須です。
ここでは、WordPress全体と
プラグインの脆弱性情報を確認できるサイトやツール、
最新情報の確認方法を5つ紹介します。
1. WordPress公式サイトのセキュリティページ
https://ja.wordpress.org/category/security
WordPressの公式サイトにセキュリティ情報のページがあります。
こここでは、WordPressのバージョンごとの変更点や脆弱性の修正内容を確認することができます。
2. WPScan
https://wpscan.com/wordpresses
WPScanは、WordPressの脆弱性を集めたデータベースとなっています。
WordPressそのものと、テーマ、プラグインそれぞれの脆弱性が報告されています。
英語で読みづらい方はブラウザの翻訳機能を使えば日本語で読めます。
3. JVN iPedia(脆弱性情報データベース)
JVN iPediaは、国内、海外問わず、脆弱性対策情報を集めたデータベースです。
日本語に対応しており、キーワード検索も可能なので、
「WordPress」と調べたり、利用しているテーマやプラグインに関する脆弱性も調べることができます。
脆弱性情報をザッと取得したい方には非常におすすめです。
4. CVE
https://www.cve.org/CVERecord/SearchResults?query=WordPress
CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)とは、
一つ一つの脆弱性を識別するための共通の識別子のことです。
「CVE」は世界中の脆弱性を管理しており、
この中にWordPress関連の脆弱性も登録されています。
セキュリティ専門家や開発者も参照する専門的なデータベースとなっています。
5. プラグインの開発者のニュース
利用しているプラグインに関する脆弱性を調べたい場合、
開発者が発信するニュースやブログ、SNSあるいはGitHubなどを参考にするのがおすすめです。
開発者の発信してくれている情報には、
「脆弱性に関する話」や「アップデート情報」が詳しく記載されています。
また、開発者自身の発信情報ということで、課題への取り組み方や、
プラグインの開発理念なども伺うことができ、長期的に信頼できそうかなども感じ取れるかもしれません。
プラグインに絞っていうのであれば、WordPressの公式のプラグインのストアページと、
開発者の発信情報を中心に見ておくといいでしょう。
🔒 プラグインアップデートはすぐに行う
WordPress管理画面に表示される「更新」通知を放置すると、
既知の脆弱性が修正されないまま残ることになります。
Web制作後も保守契約を結び、
定期的にアップデート対応することをおすすめします。
プラグインは「少ない方が良い」が基本方針
初心者ほど「便利そう!」と感じて多くのプラグインを入れがちですが、
Web制作者は厳選主義が鉄則です。
🚫 不要なプラグインは削除しよう
- 一度使わなくなったプラグインでも、有効化されたままだと脆弱性の対象になる
- 停止中プラグインもコードは存在しているため、完全に削除すべきです
✅ 代替手段の検討
- シンプルな機能はfunctions.phpや独自コードで対応できる場合もある
- 複数の機能を統合できるオールインワン型プラグイン(例:Jetpack)を検討
- テーマ開発者がセットで開発している推奨プラグインを合わせて使用する
Web制作後のメンテナンス・保守の重要性
プラグインは導入して終わりではありません。
以下のような保守タスクも制作側の責任範囲です。
- アップデートの適用(WordPress本体+プラグイン)
- エラーログ・アクセスログの監視
- バックアップの定期取得
Web制作契約に継続的な保守サービスを含めることは、クライアントにもメリットがあります。
セキュリティ事故が起きた後では遅いため、予防が何より大切です。
まとめ:便利なプラグインも、慎重に扱うのがプロのWeb制作者
- WordPressプラグインの導入は「安全性・保守性」を常に考慮
- プラグインの最終更新日と脆弱性情報のチェックは必須
- 不要なプラグインは削除し、なるべく数を絞るのが基本
- メンテナンス契約も含めたWeb制作が、長期的な信頼を生む
便利な機能が簡単に手に入るからこそ、その裏にあるリスクも理解しておくことがプロとしての責任です。
セキュリティ意識は大事!